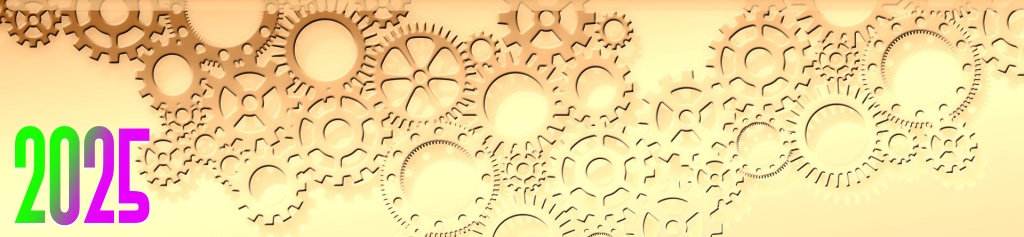▼クリックで過去の日録へ移動します。2015年以前の案内はページ最下段にあります。
●2024年
●2023年
●2022年
●2021年
●2020年
●2019年7月~12月
●2019年1月~6月
●2018年7月~12月
●2018年1月~6月
●2017年7月~12月
●2017年1月~6月
●2016年7月~12月
●2016年1月~6月
●画像はクリックで拡大、再クリックで元へ戻ります。
08月25日
二週間前の日録の捕捉――十代のとき、歌詞を書く仲間のひとりの歌詞を読んでメロディを感じ、おどろいたことがある。村野四郎の「鹿」から受けた衝撃よりもさらに古い話だ。
べつの話。「わたしは歌詞を作るのがへただから」とあるところで吉幾三が謙虚に語っている。しかしかれ自身がつくる曲と一体になると、かれの曲は古そうに見えて独自の世界を築いている。吉幾三はロックから出発した歌手。独特な味付けはそのあたりが素因か。
08月11日
かつて作曲家の船村徹は新聞のインタヴューに応えるなかで、「今は大学生でも啄木がキツツキになっちゃう。そういう時代の人が歌い手になるんですから大変です。詞が理解できない」と語っている(2000年 東京新聞)。国語力の低下などと取りざたされて久しいが、たとえば歌い手にたいする不満は北原白秋の時代にもあって、白秋は「独唱家に詩の無理解者が尠なくない」といい、「詩としては芸術家でなくてほとんど低能者のごとくに見える」ときついことをいっている(『山田耕作(ママ)全集』月報第4号1930年)。ここにおいて詩の理解は即、歌い手の表現技術として結実されていなければならないが、それはさておき、作曲家も作詞家も再現芸術における他者の国語力についてはことさら神経質のように見える▼では、啄木がキツツキになる時代にあって、作詞家たちの実力はどうなのか。現代詩も演歌に目を向けてみたrどうかなんていう声も聞こえたりするが、作詞家たちに期待しうるなにかがはたしてあるのか。青春に「はる」、人生に「みち」とかのルビは、もう慣れっこになっている。しかし売れっ子といわれているやからに限っていよいよ無法ぶりを発揮して、天の川に「ほし」、瞬間に「ゆめ」と、あげればきりがないほどにやりたい放題だ。含蓄なんかと勘違いしているのだろうか。歌謡にルビに関しても低レベルだし、詩のありようを云々する場所としては、なさけなくはないか。(中略)▼さて現代詩はと見れば…「文学そのものを理解している詩人が少ない」(井川博年=詩学2003年5月号)というのだから、どうにも、しようがない。鰐組212 編集後記 2005年10月
◆補注:手元に資料はないが、上で白秋が「詩としては芸術家ではなく低能者のごとくに見える」といっている部分は歌詞についてだろうと思われる。船村徹がいっている「詞」とおなじと解釈できるが、けつをまくってしまえばケツ、低能者といわれようと歌詞はその道を歩んでいる。歌詞に詩情が必要不可欠というわけでもない。詞は詩でなくてもいっこうにかまわない。いまの時代、作詞家は必ずしも詩人でなくてもかまわない。マンガ家でもコピーライターでもオッケーである。むしろ、詩人が詩を書けるだけでは手を出せないところにあるのが歌詞だろう。ここまでいうと開き直りか。
▼クリックで移動します。
●2015年7月~12月
●2015年1月~10月
●2014年
●2013年
●2012年3月~12月
●2011年12月~2012年2月
●2010年10月~11年6月
●2010年5月~9月
●2009年11月~10年4月
●2009年6月~10月
●2009年1月~5月
●2008年11月~12月
●2008年8月~9月
●2008年5月~9月
●2008年3月~4月